新規事業を立ち上げるには、自社に備わっている能力だけでは成功しません。新たに求められる能力をきちんと習得することが大切です。しかし、習得方法を自分で経験を積むのか、ノウハウを購入するのかにより、コストや時間が異なります。
こちらの記事では、新規事業を立ち上げるために必要なプロセスや、不足する能力を習得する方法について解説していきます。また、新規事業の成功率を高める5つのポイントについても紹介しますので、新規事業立ち上げを考える方は、ぜひ参考にしてみてください。
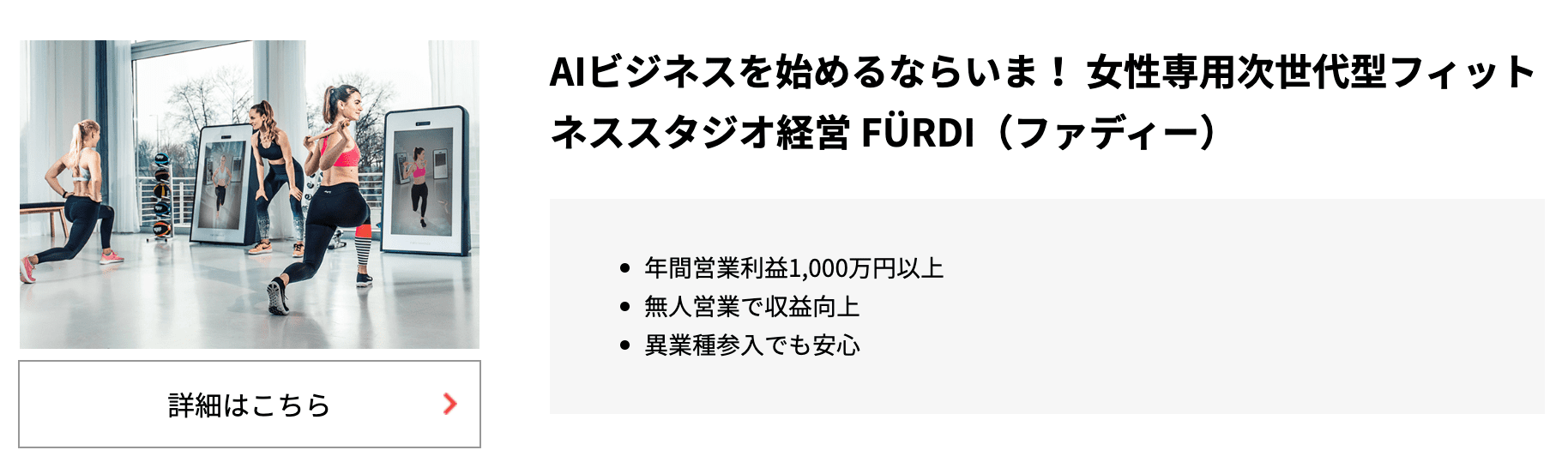

ATカンパニー株式会社
ATカンパニー(株)は、FC営業代行支援会社として2009年に創業。
乳幼児教室「ベビーパーク」をFC店ゼロから、約2年半で220加盟開発。
放課後等デイサービス「ハッピーテラス」をFC1号店から、約2年で101加盟開発
現在は、女性専用AIパーソナルトレーニング「ファディー」の支援に注力し、全国に出店拡大中。
目次
新規事業を立ち上げるにあたって「自社にある保有能力」と「新たに求められる能力」2つの側面から考えることが重要です。
自社にある保有能力とは、その会社が持っている能力を指します。保有能力には反復によって得た能力と、経験から身に付いた習熟能力が含まれます。
一方、新たに求められる能力は、新規事業の分野において必要とされる能力のことです。全くの異業種が新たな事業を行うことになるため「能力」「知識」「機能」「組織(人材)」の4つの視点を考える必要があります。
例えば、弊社が展開している女性専用のフィットネス事業を新規事業として考えた際、4つの視点は以下の通りです。
以上の視点から、自社に不足している部分をしっかり見極める必要があります。いくら完成度の高いビジネスモデルを展開することが出来ても、そのビジネスモデルを遂行するために、前述の4つの視点が備わっていなければ、ビジネスモデルは「絵に描いた餅」で終わってしまいます。
そもそも、自社にない能力が求められるにもかかわらず、既存の組織・人材を活用しても、新規事業は立ち上がらない可能性が高いでしょう。
フレームワークとは、ビジネスシーンで何かを思考するときや課題解決を図りたいときに、頭の中を整理するためのツールです。一定の枠組みを使って思考や検証を行うため、情報が整理しやすく、目標達成への解決策を見つけやすいのが特徴です。
新規事業を検討する際は、適切なフレームワークを上手に組み合わせることで、意思決定をスピーディーに行うことができます。また、説得力のある事業計画などを作る際にも、フレームワークを使った分析・検討は大いに役立つでしょう。
世の中には様々なフレームワークがあります。こちらでは、新規事業を検討する上で役立つフレームワークを7つ紹介します。
BASICS分析とは、以下5つの観点において分析するフレームワークです。
BASIC分析を活用することにより、新規事業を考える上で重要な「誰の、どんなニーズに応えていくのか?」「ビジネスプランの検討」について具体的にイメージできます。
3C分析は、3つのC、Customer(市場や顧客)、Competitor(競合)の外部環境、そしてCompany(自社)の3つの視点から分析を行うためのフレームワークです。市場を分析し潜在顧客を把握したり、競合と比較したりすることによって自社の強みや弱み、課題を抽出して “勝ち方” を見出すことができます。
3C分析について具体的に見てみましょう。まず、3つのCについては下記のような項目が挙げられます。
| 市場や顧客 (Customer) |
競合 (Competitor) |
自社 (Company) |
|---|---|---|
| ・市場規模 ・市場の成長性 ・顧客のニーズ ・顧客の消費行動 ・顧客の属性 など |
・競合各社のシェア ・各競合の特徴 ・参入・代替の脅威 ・業界ポジション ・業界ルール など |
・理念やビジョン ・事業や製品の現状 ・資本力(投資余力) ・保有する経営資源 ・ビジネスの特徴 など |
自社のことばかりを考えた経営や競合のことばかりを意識しすぎるのは良くありません。だからといって、市場や顧客のことばかりを考えて値段を決めるわけにはいかないでしょう。3点をバランス良く考えていく必要があります。
3つのバランスが整った部分は、自社の強みです。
例えば、弊社が展開をしている女性専用パーソナルトレーニングジム「FURDI」を、3C分析の観点から見出すと以下となります。
このように新規事業の一つの案として考察してみると、その事業の有効性が見えてきます。
また、現状把握、課題抽出も行うことが可能になるので、結果として対策立案や集客をする上でのマーケティング施策にも大いに活用できるでしょう。
SWOT分析は、自社内の内部環境のStrength(強み)、Weakness(弱み)、そして自社外の外部環境のOpportunities(機会)、Threat(脅威)の4つの視点から分析を行うフレームワークです。
以上のように、内部・外部の環境を整理するときに役立ちます。
自分では自社の強みがわからないという方もいらっしゃるかと思いますが、その時はターゲット層に近い顧客に実際にヒアリングをしたり、ライバルのサービスを実際に顧客として利用してみたりすると自社の強みが明確化される場合もあります。
バリュー・チェーンは、内部環境を分析するために、事業における主活動(調達、製造、販売、サービス、要するに〇〇部門と等しい)と支援活動(主活動を支えるための企業基盤、経営資源、技術開発など)のうち、どの活動で価値を生み出しているかを分析するフレームワークです。
自社が他社に比べて優れている点や弱みを明確にし、今後の施策や戦略を考えるのに役立ちます。
PDCAサイクルは、「計画(Plan)」→「実行( Do)」→ 「評価(Check)」→ 「改善(Act)」の4段階に沿って、業務を効率的に改善するためのフレームワークです。
ビジネスで広く使われているフレームワークで、4段階を繰り返すことで商品やサービスの質を高めていくことができます。
またPDCAをスムーズに回すには、全て数字で管理をしてください。数字で立てた目標や計画を実行し、数字で結果を検証して改善して数字をどんどん良くすることで、事業が成功します。
ペルソナ分析は、顧客の基本的な情報をもとに詳細なキャラクターを想定して具体的に戦略や指針を検討するために用いるフレームワークです。想定したキャラクターの精度が高いほど成功率が高くなります。そのためには、事前に綿密な調査や情報収集が重要な作業となります。
また、ペルソナ分析は、あらゆる製品やサービスに活用できるだけではなく、提供後のアフターサービスにも効果的です。
ペルソナは新規事業を利用してくれる理想の顧客像です。ペルソナを明確化することで、ターゲットとなる顧客が共感するポイントや求めているポイントも明確化され、新規事業のサービスなどに反映することもできます。
ロジックツリーは問題や原因などをツリー状に分解して見える化し解決方法を導き出す方法です。見える化することにより社内全体で問題点を理解する事ができ、また、解決すべき問題点の優先順位が明確化されます。そして各自が何をするべきか行動までが明確化されます。
ロジックツリーには下記4種類あります。
問題や原因分析だけでなく、目標設定をする際にも使えます。ツリー状に書き出すことで考えていることが整理することもできます。
自社に不足する能力、知識、機能、組織(人材)をどのように習得するか、補うか、を考えることが重要です。不足する能力をしっかり補完しないと、新規事業の立ち上げは失敗します。
「自身で経験を積み習得する」「ノウハウを買って習得する」といった選択肢がでてくるでしょう。自分で経験を積む方法を選ぶと膨大な工数や手間が発生する為、結果コストもかかります。しかし、着実に時間をかけ、習得したいという方には向いている手段です。
後者の「ノウハウを買う」とは例えば、コンサルタントの支援を受ける、またはFCに加盟することです。FC加盟の場合、基本的には習得、補うために本部が支援するケースが多く見受けられます。
弊社が展開するFCの場合は、4つの視点が習得可能です。異業種の方でも参入ができるように、本部研修、各種ツールの提供、本部スーパーバイザーによる継続的な支援、各種動画コンテンツの提供などを行っています。
新規事業の成功率を高めるポイント5つを紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
フランチャイズに加盟すると、加盟金やロイヤリティの支払いが発生したり、運営条件にルールがあったりと、面倒なイメージもあるかと思います。
しかし、フランチャイズに加盟をすればすでに成功しているフランチャイズ本部のノウハウを使用することができます。また、ネームバリューもあるので集客もうまくいくでしょう。
費用はかかりますが成功への最短ルートを進めるのがフランチャイズとなります。
ただし、フランチャイズ本部もたくさんありますので必ず事前に情報を集めて、説明会に参加するなどしてください。
新規事業を立ち上げる場合、必ず新たな費用や時間が必要となります。費用に関しては他部門で儲けた利益を投入することになりますので、大きな失敗は避けなくてはいけません。
そのためまずは大きな費用や時間をかけることはせず、まずは小さい規模でテストをしてください。小さい規模でテストをして、数字を改善することで後の大きな成功につながります。
新規事業に関わる数字はたくさんあります。売り上げ、利益、顧客数、リピート率、離脱率、登録数、解約数、などあげればキリがありません。
その数字を全てチェックすることも必要ですので、数字は社内の見えるところに掲示して見える化しておき、その数字の中から責任者が押さえるべき数字と担当者が押さえるべき数字を抽出しておきましょう。
新規事業をスタートする時など何かを始めるときはいい事しか想像できない状況となる方が多いものです。そのため、新規事業が実際にスタートして悪い状況になってきても、いつか改善できるとズルズルと続けてしまい、気がつけば会社に大きなダメージを与えてしまうということも起こり得ます。
それを避けるためには「資金が半分になったら撤退する」など事前に撤退ポイントを決めておくことが必要です。
新規事業の方向性が正しいのか間違えているのかの判断にもなりますし、事業としても傷が小さくて済み、素早く次の再起にかけることができます。
同じ業界の仲間と付き合い、横のつながりを大事にすることはとても大切なことです。しかし、周りの目を気にしすぎたり、嫌われてしまうことを恐れたりすることで、新規事業立ち上げの際に本来の力を発揮できなくなるのでは意味がありません。
本気でこの事業を成功させたいと思うなら、時には周りの目を気にせず突き進む強い気持ちも必要です。特に今までにない事業を業界で初めてスタートさせる場合などは時に同業者から浮いてしまい異端児扱いされることもあるかもしれません。
しかし、その事業が成功すればそれが業界のスタンダードにもなり、業界を活性化することにもつながります。
横のつながりも大事にしながら、時に異端児となり業界に新しい風を吹き込んでみましょう。

FC加盟の場合は、以下のようなステップが推測できます。
ここで、 FCに加盟してから成長した企業の成功事例を3つ紹介します。
創設者であるデイブ・トーマスは、もともと「ケンタッキーフライドチキン(KFC)」にFC加盟していました。KFCで学んだノウハウを活用して「ウェンディーズ」を創業し、世界第3位のハンバーガーチェーンに育て上げることができました。
「ほっともっと」は「ほっかほっか亭」のFCを展開していた企業が始めた事業です。
今では約2,800店舗と日本で最大の店舗数を誇る、持ち帰り弁当チェーンとまで成長しました。
「HARDOFF」の創業者は、「BOOKOFF」に加盟していたあと、別の事業として「HARDOFF」を設立しました。そして、2000年には新規上場を果たすまでに成長しました。
このようにFC加盟を通じて大きく成長した企業が多くあり、可能性は未知数です。
それぞれの事業には求める能力、人材像があることをしっかりと認識しましょう。その上で求めるものに合致した能力を持つ人材を確保することに、資金や工数を投下することが重要です。FC加盟という選択肢は、事業成功への近道の1つと言えるでしょう。
フレームワークを使った分析は新規事業だけではなく、既存の事業においても機能する優秀な分析ツールです。常にフレームワークを使って分析をすることで、時代の変化、顧客ニーズの変化といった市場の変化をいち早く察知することが可能です。
複数のフレームワークを組み合わせることでさらに分析の精度が増し、より深みのある情報が得られます。ぜひ活用して、新規事業の成功に役立ててみてください。